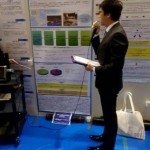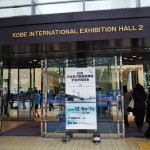こんにちは べーやんです。
最近は気温の変化が大きく、体調管理が難しい季節になってきました。
理学療法士には4月から6名の新人セラピストが入職しました。新しいことの連続で日々、忙しく頑張っている様子ですが、今回は彼らを紹介したいと思います。
あだ名:オタニ
患者様のお力になれるようにがんばります。よろしくお願いします。

あだ名:オサ
青森から来ました。とろサーモンお寿司がすきです。いっぱい食べて一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

あだ名:モカ
埼玉から来ました。笑顔絶やさず頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

あだ名:キヨシ
新潟から来ました。大量に汗をかきますが温かく見守ってください。

あだ名:ごんちゃん
新潟から来ました。新潟県出身ですがお米よりらーめんが好きです。精一杯頑張ります。宜しくお願いします。

あだ名:ゆーほ
静岡出身です。特技は人よりたくさんご飯を食べることです。一生懸命がんばりますので、よろしくお願いします。
6名とも色々な刺激を受けながら、これからも成長していく姿をリハ科全体で応援していこうと思います。








![IMG_0286[1]](/blog_reha/wp-content/uploads/2019/04/IMG_02861-150x150.jpg)
![IMG_0290[1]](/blog_reha/wp-content/uploads/2019/04/IMG_02901-150x150.jpg)