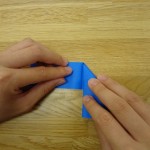こんにちは「きたじ」です。梅雨に入り雨の日も多くなりましたね。髪の毛が癖毛な私は毎日湿気との戦いを繰り広げています。
さて今回は作業療法のリハビリでおこなっている作品作りを紹介したいと思います。第一回の今回は「三角パーツ折り紙」です!
三角パーツ折り紙と聞いて、既にご存知の方もいるかもしれませんが知らない方はあまりイメージが湧かないかもしれませんね。ブログの後半でわかると思いますのでここでは説明を省かさせていただきます。
まず三角パーツ折り紙の説明の前に折り紙の歴史について少し触れたいと思います。
7世紀初めに大陸から紙の製法が日本に伝えられたのち、日本人の工夫によって薄くて丈夫な紙、「和紙」が生まれたそうです。はじめ写経や記録が紙の重要な用途でしたが、神事にも用いられるようになり、神への供物など様々なものを紙で包むようになりました。やがて供物や贈り物を包んだとき紙に折り目がつくことに着目して、包みを美しく折って飾る儀礼折が生まれてきた様です。室町時代(14,15世紀)に入ると小笠原家や伊勢家によって様々な礼法が整えられ、紙包みの礼法(儀礼折)もそのころ考えられたものです。今も使われている熨斗包みや雌蝶・雄蝶などの折り方はその名残だそうです。 やがて礼法や決まりから離れて、折り方そのものを楽しむようになったのが「折り紙」です。江戸時代に入ると紙の生産量も増え「折り紙」はいっそう庶民に親しまれるようになりました。 明治時代に入ると、「折り紙」は幼稚園教育にもとりいれられ、小学校では手工や図画でも教えるようになり、ますます盛んになりました。現在では、「折り紙」は世界各地に広まり、折紙愛好家の団体がいくつもできて盛んに活動を続けているそうです。
驚きですね。幼稚園や小学校で馴染みのある折り紙が元を辿ると神聖な儀式に使用されていたなんて。そういった物が何百年も経った現代で今も使われていることを考えるとロマンを感じますよね♪
それでは三角パーツ折り紙の作り方についてです。
① 縦:横の比が1:2になる様な折り紙を準備します(一枚の折り紙を半分にした大きさがおススメです)
② ①を図のように二回半分にします。
① ②
②
③ ②を一度だけ開き、折り目に対して図のように折ります。反対側も同様です。
④ ③をひっくり返し、角を中央に向かって折ながらひし形を作ります。
⑤ ④の横線を谷折りにし、横線を谷折りにします
⑥三角パーツの完成
③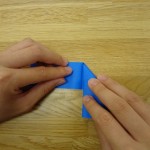 ④
④
⑤ ⑥
⑥
三角パーツ折り紙という名前の理由がわかったでしょうか。この三角形のパーツを作りたい作品の説明書に書いておる個数(簡単なものでも数百個いります)用意して組み立てに入ります。
組み立ては説明書の指示に従い土台をボンドなどで作りながらその土台に先ほど作った三角パーツを差し込んでいきます。土台の形やさし方により形が変わり、最後に目玉や鼻をつければ完成です。


三角のパーツを組み合わせることで多くの種類の作品が作れ、折り紙しか使っていないにも関わらず、見栄えも良いため患者様の中でも記念にとリハビリの合間に自室で作って退院される方もいるみたいです。上の写真は退院された患者様が作ったのを飾らせていただいています。興味がある方はぜひ挑戦してみてください♪
作品紹介は今後も引き続き行っていくので興味のある方はブログをチェックしてみてください。よろしくお願いします。













 」
」 」
」